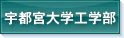初めての海外旅行、バルセロナ4日パリ3日という日程でしたが、実にいい経験をさせてもらったと思っています。パリ→バルセロナの乗り換え便は2便欠航し、どうなることやらと思っていたが、バルセロナの空港を出た瞬間、そこはもう日本とは違う別世界でした。街並み、建物のつくりが違えば道路を走っている車も外車ばかり。たまに日本車が走っていたのがどこか新鮮でした。全体的に通して、やはりバルセロナもパリも街並みは素晴らしいものがあります。まずびっくりしたのは、街並みを形成する建物のファサードが皆くっついていたことでした。建物と建物との間がないのです。日本ではありえない光景です。これは日本と欧州の土地に対する価値観の違いも否めないですが、都市を形成する段階で都市計画を重要視してきた欧州の考え方は素晴らしいものだと思います。ただ、日本は世界的にみても地震国、一方欧州はさっぱり地震の心配がないところ。欧州のあの街並みが、地震国日本で出来るのか興味深いところです。
バルセロナでは、ガウディを中心にモデルニスモ建築を多く、パリでは一般的な観光地となっているところとル・コルビジェの建築をみてきました。そのなかで僕が一番印象に残ったの、後にも先にもやっぱりガウディのサグラダ・ファミリアに圧倒されました。あのスケールに圧巻、装飾に圧巻、ガウディの考えにまた圧巻です。サン・パウ病院からサグラダ・ファミリアまで続くガウディ通りからみたサグラダ・ファミリアは、そしてそこを歩いて近づくに連れてだんだん目の前にくるサグラダ・ファミリアは本当に感動ものでした。
サグラダ・ファミリアは本当に見所が満載でした。外観は何度か写真で見たことはあったのですが、内部の知識は全くなく、そこは想像もしない世界が広がっていました。まだ未完成なので内部も一部しか見れなかったわけですが、驚くのには十分でした。中は十分に天井が高く、壁には結構な面積の窓がトップライトを含め、ありました。カテドラルやパリのノートル・ダム寺院はそんなに窓はなかったはず、あっても大きな窓は見事なステンドグラスだけだったと思います。サグラダ・ファミリアも勿論ステンドグラスはありますが、こうした普通の窓が思えば新鮮な感じがします。今の時代に建設している大聖堂としてそれが昔との違いなのかなと思います。それと驚くべきは柱。規則的に並べられた支柱の上部はなんと枝分かれしていました。そして枝分かれした各々の柱はそれぞれ天井に溶け込んでいくように接合されている、ガウディは屋根や支柱といった構造的要素を一つの有機体に総合しようとしたために、こんなに複雑になってしまったようです。
そして支柱の枝分かれは“樹木式構造”と呼ばれ、ガウディが自然主義者であることがわかります。ガウディはこの樹木式構造の部分をきちんと構造設計しました。鉛直方向だけでなく、風などの水平荷重についても考慮したようです。しかし、地震については計算しなかったようです。地震について計算しなくていいなんて全く恵まれた土地です。日本なら樹木式構造はおそらく無理でしょう。自然造形は規則性のない曲線が最大の特色であり、建築に規則性のない曲線は不適切である、この規則性のない曲線をどうにかして規則的な曲線で表現しようという幾何学との闘いが始まりました。これがガウディが幾何学者と言われる由縁です。
サグラダ・ファミリアの施工はガウディが残した図面や模型が頼りです。しかし、それらは内戦などでほとんどが崩壊、紛失してしまいました。その復元のため図面はCADを使用し、幾何学的観点から解明しようと試みているのですが、自然造形の曲線はCADではものすごく表現するのが困難なようです。逆に模型にした方が容易なんだそうです。今はCADで設計するのが当たり前で、直線も曲線もCADに頼った線を使用している建築物が多い気がします。ただ、これは誰のせいでもなく仕方がないのです。コンピューター技術が発達しすぎたためなのです。ガウディは今の時代に生まれてこなくて本当に良かったと思います。ただ、CADがありふれた時代になった今、改めて手描きの良さが見直されています。CADはあくまでデザインを支援するソフト、CADに頼りすぎてCADに縛られる…、そんなことはないようにしたいです。ともかくも1882年に着工され、竣工まで約150年かかると言われているサグラダ・ファミリア。建設がこのままの調子で進めば、2040年頃完成するという。完成した暁には、是非もう一度バルセロナまで足を運び、サグラダ・ファミリアの完全な姿を拝みたいものです。
バルセロナでは、ガウディを中心にモデルニスモ建築を多く、パリでは一般的な観光地となっているところとル・コルビジェの建築をみてきました。そのなかで僕が一番印象に残ったの、後にも先にもやっぱりガウディのサグラダ・ファミリアに圧倒されました。あのスケールに圧巻、装飾に圧巻、ガウディの考えにまた圧巻です。サン・パウ病院からサグラダ・ファミリアまで続くガウディ通りからみたサグラダ・ファミリアは、そしてそこを歩いて近づくに連れてだんだん目の前にくるサグラダ・ファミリアは本当に感動ものでした。
サグラダ・ファミリアは本当に見所が満載でした。外観は何度か写真で見たことはあったのですが、内部の知識は全くなく、そこは想像もしない世界が広がっていました。まだ未完成なので内部も一部しか見れなかったわけですが、驚くのには十分でした。中は十分に天井が高く、壁には結構な面積の窓がトップライトを含め、ありました。カテドラルやパリのノートル・ダム寺院はそんなに窓はなかったはず、あっても大きな窓は見事なステンドグラスだけだったと思います。サグラダ・ファミリアも勿論ステンドグラスはありますが、こうした普通の窓が思えば新鮮な感じがします。今の時代に建設している大聖堂としてそれが昔との違いなのかなと思います。それと驚くべきは柱。規則的に並べられた支柱の上部はなんと枝分かれしていました。そして枝分かれした各々の柱はそれぞれ天井に溶け込んでいくように接合されている、ガウディは屋根や支柱といった構造的要素を一つの有機体に総合しようとしたために、こんなに複雑になってしまったようです。
そして支柱の枝分かれは“樹木式構造”と呼ばれ、ガウディが自然主義者であることがわかります。ガウディはこの樹木式構造の部分をきちんと構造設計しました。鉛直方向だけでなく、風などの水平荷重についても考慮したようです。しかし、地震については計算しなかったようです。地震について計算しなくていいなんて全く恵まれた土地です。日本なら樹木式構造はおそらく無理でしょう。自然造形は規則性のない曲線が最大の特色であり、建築に規則性のない曲線は不適切である、この規則性のない曲線をどうにかして規則的な曲線で表現しようという幾何学との闘いが始まりました。これがガウディが幾何学者と言われる由縁です。
サグラダ・ファミリアの施工はガウディが残した図面や模型が頼りです。しかし、それらは内戦などでほとんどが崩壊、紛失してしまいました。その復元のため図面はCADを使用し、幾何学的観点から解明しようと試みているのですが、自然造形の曲線はCADではものすごく表現するのが困難なようです。逆に模型にした方が容易なんだそうです。今はCADで設計するのが当たり前で、直線も曲線もCADに頼った線を使用している建築物が多い気がします。ただ、これは誰のせいでもなく仕方がないのです。コンピューター技術が発達しすぎたためなのです。ガウディは今の時代に生まれてこなくて本当に良かったと思います。ただ、CADがありふれた時代になった今、改めて手描きの良さが見直されています。CADはあくまでデザインを支援するソフト、CADに頼りすぎてCADに縛られる…、そんなことはないようにしたいです。ともかくも1882年に着工され、竣工まで約150年かかると言われているサグラダ・ファミリア。建設がこのままの調子で進めば、2040年頃完成するという。完成した暁には、是非もう一度バルセロナまで足を運び、サグラダ・ファミリアの完全な姿を拝みたいものです。